 列車の旅
列車の旅 JR大阪駅地下ホーム
前記事梅田界隈を書きながらJR大阪駅地下ホームのことが気になりだした。 存在は当然知ってはいたがそう大騒ぎすることでないかなくらいに考えていた。 しかし、気になりだしたらもう、行ってみるしかない。 ここ、新大阪駅から新しいホームに乗り込むこ...
 列車の旅
列車の旅 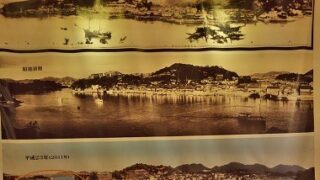 フェリーの旅
フェリーの旅  列車の旅
列車の旅  列車の旅
列車の旅  列車の旅
列車の旅  中国
中国  モネの池
モネの池  アジサイ
アジサイ  列車の旅
列車の旅  列車の旅
列車の旅