 古民家
古民家 古民家を訪ねて 南部の曲家(旧藤原家住宅)
東北地方の農家は、広い平野にそれぞれの位置を占めた散村を形作り、敷地背面に防風林をもつ永い独立した生活を送った姿をとどめています。 移設元旧岩手県紫波郡矢巾町煙山 昭和39年(1964)に移築されたこの民家も、かつては一つ家(ひとつや)と呼...
 古民家
古民家  朝日・夕日
朝日・夕日  日本の町並み
日本の町並み  日本の町並み
日本の町並み  東北
東北  日本の町並み
日本の町並み 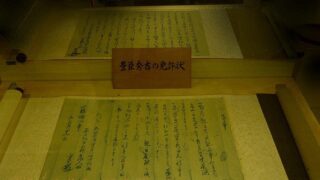 日本の町並み
日本の町並み  日本の町並み
日本の町並み  東北
東北  名城の旅
名城の旅