 モネの池
モネの池 どことなくモネの池 大原野神社
大原野神社の創建は平安京遷都以前、桓武天皇の長岡京遷都まで遡ります。 延暦3年(784年)に藤原氏の氏神である奈良春日大社の神々をこの地に分霊し勧請した事が始まりとされ、別名「京春日」とも呼ばれている古社です。 参道はまるで緑のトンネル~夏...
 モネの池
モネの池  モネの池
モネの池  ハス
ハス  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  四国
四国  四国
四国 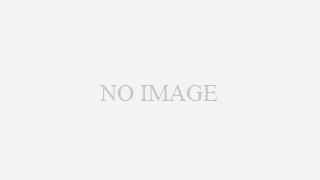 京都府
京都府