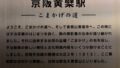隠元禅師は中国福建省福州府福清県の黄檗山萬福寺の住持だった
日本からの度重なる招請に応じて、承応3年(1654年)に弟子20人他を伴って来日。
後水尾法皇・徳川幕府の崇敬を得て、宇治大和田に約9万坪の寺地を賜り、寛文元年(1661年)に禅寺を創建した。
関連記事:宇治茶発祥の地 黄檗山 萬福寺
.jpg)
惣門は修復工事の最中であった。
.jpg)
三門の窟門(くつもん)、江戸時代、1768年、山門の両側に開いた通り口。
左の白雲関(窟門)、あの、総門の「第一義」を書いた5代・高泉の書。
修行者への心構え、自覚を促している。
対聯(たいれん)に言う「門外已(すで)に無差別の路(みち)」「雲辺(うんぺん)又一重(いちじゅう)の関有り」。
.jpg)
右の通霄路(つうしょうろ)
.jpg)
三門の手前に天真院という塔頭がある。
.jpg)
天真院の前は趣のある庭だ
天真院の横には精進料理の普茶料理が食べられる銀杏庵がある
総門をくぐると三門がある
三間三戸・重層の楼門作りで、左右に裳階・山廊がある。
総門から法堂にかけ続く参道は、菱形に敷かれた平石、さらに両側を石條で挟んである。
この黄檗様敷石は、龍の背の鱗を表すという。
菱形の石の上に立てるのは住持のみに限られている。
江州日野田中藤左衛門・矢野儀右衛門の寄進による。
.jpg)
三門正面の「黄檗山」「萬福寺」は隠元禅師の書。
萬福寺の額や聯は、その建築同様に、重要文化財に指定されています。
額40面、聯44対、榜牌13面、それらの下書き14幅です。
なかでも、隠元、木庵、即非は「黄檗三筆」とも称される能筆でした。
.jpg)
中和門院(ちゅうわもんいん)御宮址は後水尾法皇のご生母、中宮前子の宮址。
.jpg)
松隠堂の屋根にうっすらと雪が積もっている。
松隠堂(しょういんどう)は隠元の隠居所として寛文3年(1663)に創立。
境内の石畳は全域が菱形を一列に連ねたものですがこの開山堂の門の内側の石畳は氷裂紋と呼ばれる様式の石畳です
.jpg)
開山堂の扉に掘られた「桃符」と呼ばれる桃の実形の飾り。
桃は魔よけの意味を持つ。
開山堂(かいざんどう)は延宝3年(1675)の創立。
隠元禅師の尊像を奉祀している。
.jpg)
寿塔(寿蔵・真空塔)(重文)、江戸時代、1663年建立、隠元の墳墓で、生前に築造された。
円窓の戸板題「寿蔵」は隠元書。
額「眞空塔」は霊元天皇書。
.jpg)
合山鐘(がっさんしょう) 、雲文梵鐘。
6代・千呆により1696年に再鋳された。
開山堂、寿蔵、舎利殿で行われる儀式の出頭時にのみ鳴らされる。
.jpg)
石碑亭、亀趺(きふ)の上に、江戸時代、1673年に後水尾天皇から隠元に贈られた「特賜大光普照國師塔銘」の刻文がある。
趺とは石碑の台のことで、亀形のものを亀趺、一般につくられた方形台を方趺と称しています。
.jpg)
この時期ナンテンはきれいに色づいています。
.jpg)
鼓楼(重文)、江戸時代、1679年建立、重層入母屋造、本瓦葺。二階四周に縁と逆蓮柱付の匂欄を廻らし、大棟(屋根)両端に鯱を置く。
階上に梵鐘がある。
鼓楼は鐘楼と相対し、朝4時半開静、夜9時の開枕に大鐘と太鼓により、時刻と消灯、起居動作の始終を知らせる。
また賓客来山の際にも、鐘鼓交鳴して歓迎を表わす。
.jpg)
大雄宝殿、4本の巨大な聯(れん)(隠元、木庵、即非、彗林、高泉、悦山道宗など筆)が掛けられている。
「聯」とは聞きなれない言葉ですが、建物の柱や壁の左右に一対で掛けられる板で、含蓄のある禅語などが書かれています。
このように長いものは日本では珍しいという。
床は黒い敷瓦の四半敷。
.jpg)
大雄宝殿、天井付近に掲げられている明治天皇筆「真空」の扁額
.jpg)
大きな丸い木魚、読経の際に使われる。
木魚は黄檗宗が日本にもたらし、その後、他宗にも普及した。
.jpg)
雲版(うんばん)を打つ僧侶
雲版は、朝と昼の食事と朝課の時に打つ。
青銅製。
江戸時代、1661年頃設置。
.jpg)
お供え物を下げる僧侶。
.jpg)
生飯台(さばだい)、鬼界の衆生に施す飯を載せる。
先ほどの僧侶が米粒を置いていきました。
.jpg)
蛇腹天井(黄檗天井)と呼ばれるアーチ形の天井。
.jpg)
襷(たすき)勾欄、中央チベット、中国などで見られるという 日本では珍しい意匠という
.jpg)
法堂(はっとう)(重文)、江戸時代、1662年建立、もとは円通殿といった。
1664年に法堂となる。
内部には須弥壇のみを置き、仏像は安置されていない。
上堂や住持の晋山式などに使う。
須弥壇上の額「法堂」は隠元の書で、黄檗山では唯一の楷書による。
昆尼垣の額は4代・独湛書、重文指定。
内部は非公開。
.jpg)
聯燈堂、江戸時代、1789年建立、1973年再建。
.jpg)
キハダの木が植えられていた、黄檗(おうばく)はキハダ (植物)の別名。
.jpg)
卍くずしのデザインによる高欄はまさに中国的
.jpg)
左は文華殿 – 三門をくぐって右手にある宝物館。
宗祖三百回忌を機に昭和47年(1972年)に建てられたもので、展示室のほか、黄檗文化研究所を設置する。
.jpg)
河口慧海にチベット行きを決意させたのが、京都・宇治にある萬福寺・塔頭「宝蔵院」の一切経の版木だった
.jpg)
明治から大正時代にかけ2度もチベットを訪れ一切経など仏典を手に入れた慧海はネパールで数年間勉強してヒマラヤを越えたので、後にネパール大王に宇治・黄檗寺の「黄檗版一切経」を献上したとされる。
堺散策河口 慧海(かわぐち えかい、1866年2月26日(慶応2年1月12日) – 1945年(昭和20年)2月24日)は、黄檗宗の僧侶
日本100名城のツアーを探す
萬福寺への行き方歩き方
・住所:〒611-0011 京都府宇治市五ヵ庄三番割34
・電話:0774-32-3900
・拝観時間:9:00~16:30
・拝観料:500円
・アクセス:JR奈良線、京阪電車宇治線の「黄檗」駅から徒歩約10分
宿泊施設
おすすめの旅行プラン
日本100名城巡りを始めて足かけ3年、足でたどった 名城を訪ねる旅
この記事に掲載されている情報は、公開時点のものです。

.jpg)
.jpg)
.jpg)