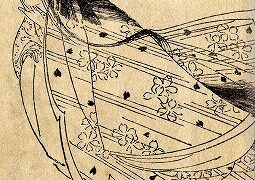 京都府
京都府 ライバルを救った小町の慈悲心「草子洗小町」
小町零落説の背景には、あまたの貴公子を虜にした小町に対しての男性諸氏のひがみ根性があったといわれる「深草少将の百夜通い」は美化されているが、現代なら一歩間違えばストーカー行為か。今回は小町を称える奇跡談を。実際のところ、当時の小野小町の姿を...
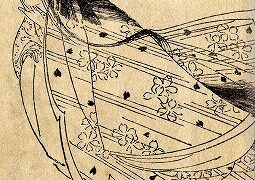 京都府
京都府  東北
東北  大阪府
大阪府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  九州
九州  京都府
京都府  大阪府
大阪府