 北陸
北陸 福井城
復元なった山里口御門と櫓門・廊下橋廊下橋。藩主は西三の丸御座所に居住し、そこから本丸内の藩政所へ通うための専用の橋が廊下橋であった。桜はすでに盛りを過ぎている。改装なった福の井「福の井」は慶長6年(1601)の北ノ庄城(後の福井城)築城当時...
 北陸
北陸  北陸
北陸  北陸
北陸  東海
東海  東海
東海  東海
東海  東海
東海  東海
東海  東海
東海 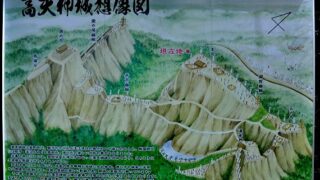 東海
東海  東海
東海  東海
東海