 甲信越
甲信越 桜の名所 高遠城
今回は信州の名城巡りです往復1,100㎞超のバス旅、お尻が痛くなりました。まずは、絵島囲み屋敷でお馴染みの高遠城。まずは駒ヶ根で昼食です。本来なら木曽駒ケ岳が望めるのだが、今朝ほど駆け抜けていった台風26号の余波でご覧の通り。進徳館、最後の...
 甲信越
甲信越  東海
東海  北海道
北海道  北海道
北海道  北海道
北海道 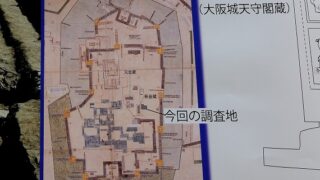 大阪府
大阪府  東北
東北  東北
東北  東北
東北  東海
東海  東海
東海  九州
九州