 滋賀県
滋賀県 日本最古 伝教大師坐像を祀る「観音寺」
山号は伊富貴山。本尊は十一面千手観音。通称:大原観音寺。仁寿年間(851年 - 854年)、三修によって創建された。もとは伊吹山四大護国寺として法相宗に属していたが、弘和(永徳)3年(1383年)に天台宗に改めた。長浜城主の羽柴秀吉が鷹狩り...
 滋賀県
滋賀県  滋賀県
滋賀県  大阪府
大阪府  滋賀県
滋賀県  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府 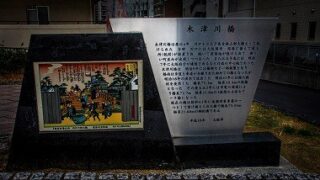 大阪府
大阪府  兵庫県
兵庫県  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府