 九州
九州 口之津から鬼池へ
空模様は相変わらずはっきりしないまま、ただ無性に蒸し暑い。今日は島原の口之津から天草の鬼池へフェリーで渡る。どちらの港も何もない殺風景なたたずまいを見せるが歴史的には多くの事件、出来事があった。口之津町(くちのつちょう)は、島原半島の南端の...
 九州
九州  九州
九州  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府  京都府
京都府  九州
九州  京都府
京都府 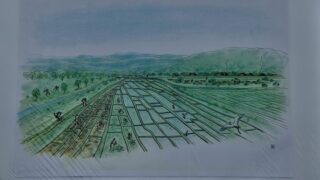 大阪府
大阪府  京都府
京都府