 四国
四国 龍馬の育ったまちを訪ねる
坂本龍馬が生まれた高知市上町にある記念館では、昔の上町の町並みを半立体模型で再現龍馬の精神的なバックボーンを育てた上町という町を紹介しています。龍馬の生まれたまち記念館が路面電車 上町一丁目下車(はりまや橋乗り換え)すぐのところにある。入り...
 四国
四国  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府  奈良県
奈良県  奈良県
奈良県  奈良県
奈良県  奈良県
奈良県  奈良県
奈良県  奈良県
奈良県 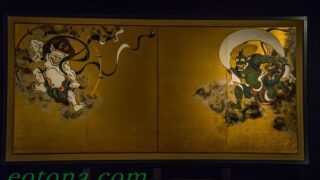 京都府
京都府