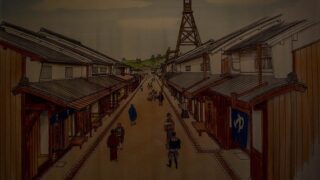 大阪府
大阪府 江戸時代の大阪へ
天神橋六丁目、角のビル、大阪くらしの今昔館、9階に上るとあら不思議、そこはなにわの町の中。案内にある町の姿。ぶらり歩けば江戸時代に迷い込む。木戸門をくぐると大通りの両側に、風呂屋、本屋、建具屋、小間物屋、唐物屋、呉服屋、薬屋が並び、町会所の...
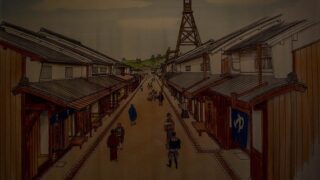 大阪府
大阪府  北陸
北陸  北陸
北陸  北陸
北陸  北陸
北陸  北陸
北陸  北陸
北陸  北陸
北陸  北陸
北陸  京都府
京都府  北陸
北陸  北陸
北陸