 奈良県
奈良県 飛鳥資料館
1970年閣議において飛鳥地域の出土品などを保管するための施設の建設が決定され、数寄屋風のコンクリート建築による資料館が建てられ、1975年3月16日に開館飛鳥時代における倭国の中心であった飛鳥地域で発掘された多くの出土品を展示するとともに...
 奈良県
奈良県  奈良県
奈良県  奈良県
奈良県  奈良県
奈良県  奈良県
奈良県 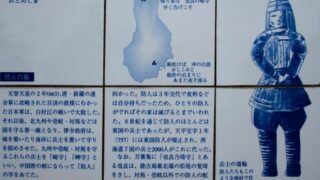 九州
九州  九州
九州  九州
九州 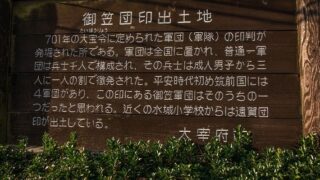 九州
九州  兵庫県
兵庫県  大阪府
大阪府  大阪府
大阪府