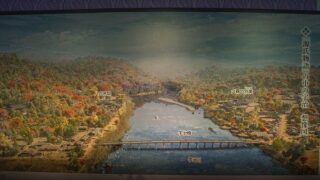 奈良県
奈良県 宇治の間
宇治の間は、光源氏の息子、薫、孫の匂宮が登場する源氏物語の第三部のうち「宇治十帖]と呼ばれる部分薫、匂宮、大君、中の君、そして浮船の五人が宇治の地で綾なす恋の物語桐壺院の八の宮(第八皇子)で、光源氏の異母弟である。冷泉院の東宮時代、これを廃...
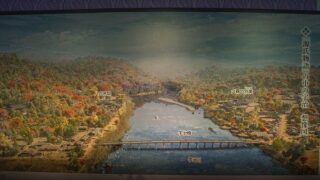 奈良県
奈良県  滋賀県
滋賀県  北陸
北陸  北陸
北陸  大阪府
大阪府  兵庫県
兵庫県 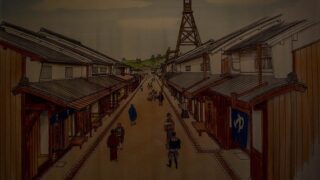 大阪府
大阪府  北陸
北陸  地域
地域  大阪府
大阪府  地域
地域  九州
九州