 京都府
京都府 聖武天皇勅願 海住山寺
当寺の創建事情については必ずしも明らかではないが、寺伝では天平7年(735年)、 聖武天皇の勅願により良弁(奈良東大寺の初代別当)を開山として藤尾山観音寺という寺号で開創したという伝承によれば、聖武天皇は、平城京の鬼門にあたる現・海住山寺の...
 京都府
京都府  京都府
京都府 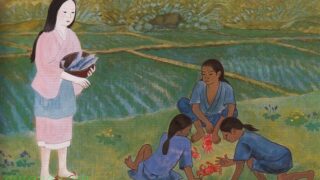 京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府