 中国
中国 岡山城(烏城)
後楽園 岡山藩2代目藩主・池田綱政(つなまさ)が自ら憩いの場として築いた大庭園。 領民の入園も認め、能を好んだ綱政は自ら舞う姿を見せたり、継政以後の藩主たちは、参勤交代で岡山を留守にする間は日を決めて庭を見せていたという。 1934(昭和9...
 中国
中国  中国
中国  中国
中国 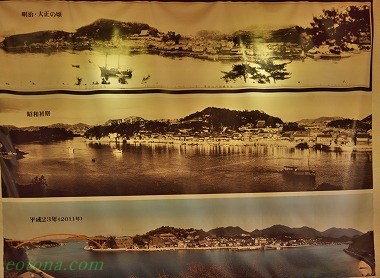 フェリーの旅
フェリーの旅  中国
中国  中国
中国  中国
中国  フェリーの旅
フェリーの旅  中国
中国  中国
中国  中国
中国  中国
中国