 京都府
京都府 小野篁の冥土通い 六道珍皇寺
小野篁関連のブログ集 代表歌 参議篁(小野篁)(百人一首より) わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人には告げよ海人の釣舟(『百人一首』11番) 泣く涙雨と降らなむわたり川水まさりなばかへりくるがに(『古今和歌集』) 「六道」とは、仏教の教義で...
 京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府 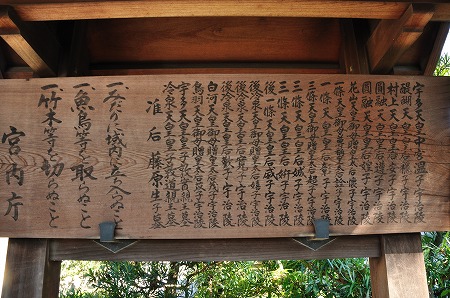 京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府  京都府
京都府